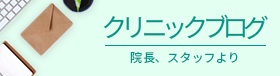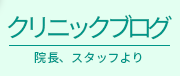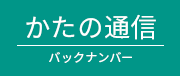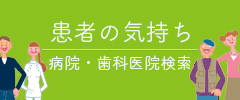肘部管症候群
【肘部管症候群とは】
肘部管症候群とは、肘の内側にある「肘部管」というトンネルを通る尺骨神経が、圧迫や牽引を受けることで、手のしびれや痛み、筋力低下などの症状が現れる疾患です。

肘部管は、上腕骨の内側上顆と尺骨肘頭という骨の隆起部、そしてそれらをつなぐ靭帯や筋肉で構成される狭いトンネルです。尺骨神経は、首から腕、そして手へと伸びる神経で、肘部管を通って前腕や手の筋肉を支配しています。
この肘部管内で尺骨神経が圧迫されると、神経の働きが障害され、特有の症状が現れます。
肘部管症候群の原因は多岐にわたりますが、主なものとしては以下のようなものが挙げられます。
- 肘の変形: 過去の骨折や脱臼などの後遺症として、肘の形が変形し、肘部管が狭くなることがあります。
- 肘の使いすぎ: 長時間の肘の曲げ伸ばしや、肘を酷使する作業などによって、肘部管内の組織が炎症を起こし、神経を圧迫することがあります。
- ガングリオンなどの腫瘤: 肘部管内に腫瘤ができることで、神経が圧迫されることがあります。
- その他: 生まれつき肘部管が狭い、糖尿病などの全身疾患が原因となることもあります。
【肘部管症候群の症状】
肘部管症候群の主な症状は、手のしびれや痛み、筋力低下です。
- しびれ・痛み: 手の小指側と薬指の小指側の半分にしびれや痛みを感じることが多いです。肘の内側にも痛みを感じることがあります。特に、肘を曲げた状態を長く続けると症状が悪化しやすいです。
- 筋力低下: 手の筋肉、特に小指を動かす筋肉や、指を横に開閉する筋肉が弱くなることがあります。細かい作業がしにくくなったり、物がつかみにくくなったりすることがあります。
- 鷲手変形: 進行すると、小指と薬指が曲がったまま伸びにくくなる「鷲手変形」という状態になることがあります。
症状は、初期の頃は間欠的に現れることが多いですが、進行すると持続的に現れるようになります。
【検査・診断】
肘部管症候群の診断は、問診、理学的検査、神経学的検査、画像検査などに基づいて行われます。
- 問診: いつから、どのような時に症状が出るか、仕事や生活習慣などを詳しくお伺いします。
- 理学的検査: 肘の腫れや変形の有無、肘の可動域などを確認します。
- 神経学的検査:
- ティネル徴候: 肘の内側を叩くと、手のしびれが誘発されるかを確認します。
- フローマン徴候: 紙をつまむ際に、親指の付け根の筋肉が働くかを確認します。
- 肘屈曲テスト: 肘を曲げた状態を一定時間保持し、症状が誘発されるかを確認します。
- 画像検査:
- レントゲン検査: 骨の変形や肘関節の状態を確認します。。
- 神経伝導速度検査: 神経の電気的な活動を測定し、神経の圧迫部位や程度を評価します。。
- その他の検査: 必要に応じて、MRI検査などを行うこともあります。
【肘部管症候群の治療】
肘部管症候群の治療は、症状の程度や原因によって異なります。
保存療法
初期の頃や、症状が軽い場合には、保存療法を行います。
- 安静: 肘を曲げた状態を長時間続けることを避け、肘に負担のかからないようにしましょう。
- 薬物療法: 痛み止め(内服薬や外用薬)を用いることで、痛みを和らげます。
- 装具療法: 夜間などに肘を軽く伸ばした状態で固定する装具を装着することで、神経への圧迫を軽減します。
- リハビリテーション: 神経を滑りやすくする運動や、手の筋肉を強化するトレーニングなどを行います。
手術療法
保存療法で症状が改善しない場合や、筋力低下が進行している場合には、手術療法を検討します。
- 肘部管開放術: 肘部管を構成する靭帯や組織を切開し、神経への圧迫を解除する手術です。
【肘部管症候群の予防】
肘部管症候群を完全に予防することは難しいですが、発症のリスクを減らすために、以下の点に注意することが大切です。
- 肘の使いすぎを避ける: 長時間の肘の曲げ伸ばしや、肘を酷使する作業は避けましょう。
- 正しい姿勢: デスクワークなど、長時間同じ姿勢を続ける場合は、適度に休憩を挟み、正しい姿勢を保つように心がけましょう。
- 肘への負担を軽減する: 重い物を持ち上げる際には、肘だけでなく、体全体を使って持ち上げるようにしましょう。
- 早期発見・早期治療: 手のしびれや痛みなどの症状が現れたら、早めに医療機関を受診しましょう。
【十日市場、霧が丘のかたの整形外科クリニックへ相談を】
横浜市緑区、十日市場、霧が丘のかたの整形外科クリニックでは、肘部管症候群の診断と治療を行っています。患者さんの症状や状態に合わせて、適切な治療法を選択し、リハビリテーションや日常生活での注意点なども丁寧に指導いたします。手術が必要と判断される場合には、適切な医療機関をご紹介いたします。
【よくある質問】
Q:肘部管症候群は放置するとどうなりますか?
A:放置すると、手の筋力低下が進行し、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。また、症状が慢性化し、治療に時間がかかることもあります。
Q:肘部管症候群に良い運動はありますか?
A:神経を滑りやすくする運動や、手の筋肉を強化するトレーニングが効果的です。専門家の指導のもと、適切な運動を行うようにしましょう。